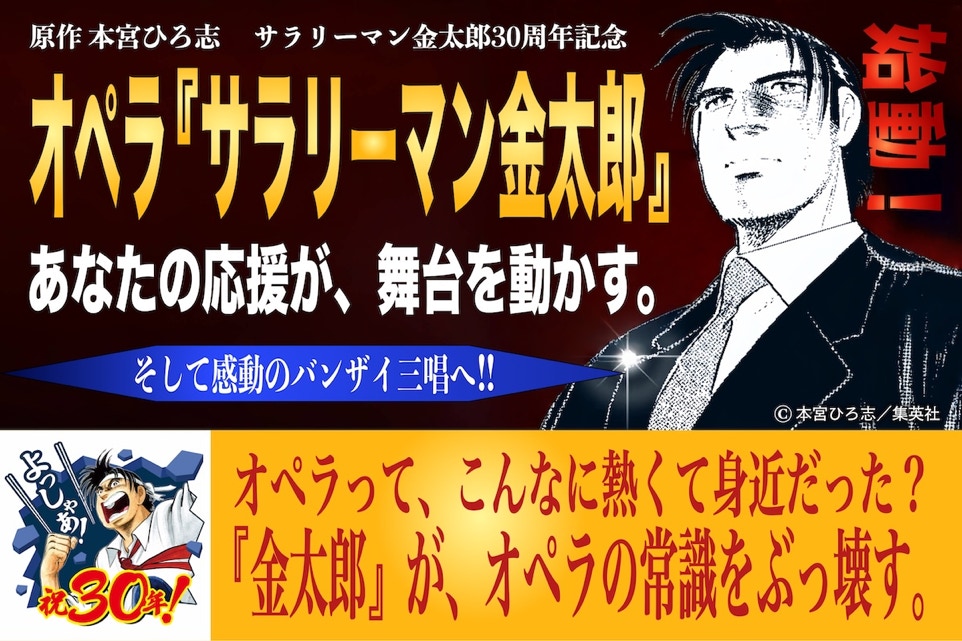対 談
栗原峻希(バリトン歌手)×林田直樹(音楽ジャーナリスト・評論家)
~オペラ「サラリーマン金太郎」の上演を前に~
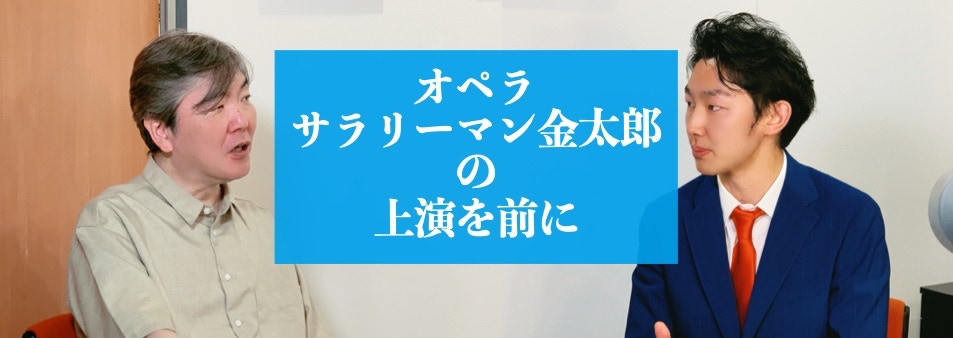
目次
●札幌での「ドン・ジョヴァンニ」出演とバリトンの役柄
林田: 栗原さんは、3月に札幌でモーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」で題名役を歌われましたよね。
栗原: はい。
林田: あれは札幌文化芸術劇場hitaruの自主制作による非常に大切なプロダクション(園田隆一郎指揮札幌交響楽団、粟國淳演出)で、そこで主役に抜擢されたわけじゃないですか。残念ながら私は札幌には観に行けなかったんですが、栗原さんのことはもちろんチェックしていましたよ。やっぱりバリトン歌手にとって、ドン・ジョヴァンニは特別な役ですから。
栗原: 本当にその通りですね。
林田: 歌われてみてどうでしたか?
栗原: そもそも、バリトンで主役、つまりタイトルロールというのは、数えればいくらでもありますが、うんとメジャーな作品となると、本当に「ドン・ジョヴァンニ」くらいじゃないですか。まあ、「フィガロの結婚」もそうですし、ヴェルディの幾つかのオペラもありますけど…。バリトンという声は、オペラの歴史を考えてみると、モーツァルトくらいから主役になったり、重要な役を歌うことが多くなってきたと感じます。
林田: 栗原さんは高校生の時にオーケストラでチェロを弾いていたそうですね。ロマン派になるにつれて、オーケストラでは中低音が重要になってくるんです。つまり低音が強化されてくるのが19世紀の音楽の全般的な傾向で、だんだん深くて重い音を好むようになってきた。だからロマン派時代のオペラでも、バリトンは特に重要ですよ。ドン・ジョヴァンニがバリトンであることは、すごく象徴的なことです。
栗原: ある意味、ロマン派の先駆けのようですよね。実際に舞台でやってみて本当にびっくりしました。これが当時の客席にどんな反応として捉えられたんだろう?と。終わって、みんなポカーンとしてたんじゃないか。これが当たり前のように「素晴らしい」となるのは、今だからこそであって、当時としてはすごく時代に先んじていた作品だったと思います。
林田: ヘンデルなどのバロック・オペラの時代は、ある意味、神話的な声が重要でしたよね。
栗原: そうですね。それがだんだん神話から、オペラも身近な主人公になっていき、物語もリアルになっていく。ヴェリズモ(現実主義)のように、実際の事件を題材に描く流れになっていく。「ドン・ジョヴァンニ」は、その先駆けですね。そういえば、「ドン・ジョヴァンニ」のケッヘル番号って527番ですけど、僕の誕生日も5月27日なんですよ。
林田: それはすごい!
栗原: 最初見たとき、なんで僕の誕生日が書いてあるんだろうって思った(笑)。
林田: 生まれつきのドン・ジョヴァンニですね(笑)。でもそれだけじゃなくて、栗原さんの歌うヴェルディの「マクベス」なども録音で聴きましたが、どれも素晴らしかったです。ああいう悲劇的な主人公の重い声がぴったりなんですね。
栗原: 明るい役も好きですけど、どっちかというと悲壮感がある役が好きですね。
林田: バリトンって、ナンバー2だったり、悪役だったり、渋いところを攻めるじゃないですか。色恋だけじゃない、硬派なメッセージを担うことも多い。
栗原: それがバリトンの良さですよね。

●新作オペラ「サラリーマン金太郎」の主役がなぜバリトンか
林田: 今回の「マネーウォーズ編」も色恋の話ではないですよね。やはり社会性のある話になっている。
栗原: 本当にその通りです。社会でみんなが「こう思っているんだ」ということを、代わりに矢島金太郎がすべて言ってくれる。そういうスカッとする作品です。「サラリーマン金太郎」は、元々漁師だった金太郎が、ひょんなことから会社に入社するところから始まります。
林田: 最も非サラリーマン的な人物ですよね。
栗原: そうです。その彼がサラリーマンになった時、逆にサラリーマンの常識に対して「なんだそれは」と問題を投げかける。するとみんなも「なんでこうなってるんだろうな」「こうした方がいいはずだ」と気づき始める。金太郎がいることで、全体の流れが動いていくストーリーです。
林田: 金太郎は自由で強い意志を持っていますが、一方でサラリーマンには「社畜」という言葉があるように、飼いならされた弱いイメージもあります。でも金太郎は「サラリーマンをなめるな」と言いますよね。彼は、会社に属して頑張っているサラリーマンを決して馬鹿にしない。
栗原: そこが本当に重要な軸です。僕たち一人ひとりが社会の歯車かもしれないけれど、その歯車が一つでも欠けたら機能しなくなる。「一人ひとりが大事なんだ」ということを訴えかけてくれる作品です。金太郎自身も社長になりそうになるけれど、「俺はそういうのはやりたくない」と断る。一人ひとりの人間をすごく大事にしているんです。
林田: 原作のマンガでは最初に、弱そうなおじさんが若者に絡まれているのを助けるシーンがありますよね。彼は、見た目で判断されがちな人たちのことも、直感的に理解できる素晴らしい優しさを持っています。
そして今回は「マネーウォーズ編」。今の世の中は拝金主義になっていると思うんです。お金や数字に心を支配されている。それに対して金太郎の存在は、人間的なものを取り戻させてくれる、異議を申し立ててくれる存在ですよね。
栗原: まさにその通りだと思います。「本当に大切なものは何なんだ」と問いかけてくる。彼自身は拝金主義ではなく、大金をもらってもそこに興味がない。
林田: お金に支配されない。そこがすごいですよね。
栗原: それだけの器の大きさがある。人間が生きる上で一番重要なことは何か、その芯を突いているのが矢島金太郎の魅力だと思います。
林田: 今回、金太郎の役がテノールではなくバリトンというのも大きなポイントだと思っています。普通のオペラではテノールが英雄で、バリトンは悪役やナンバー2じゃないですか。それが、バリトンが金太郎をやる。ここにすごく意味があると思います。
栗原: やはりバリトンだろうな、と思いますね。一番人間らしいし、人間としての説得力を担う部分は、オペラの中ではバリトンなんだろうなと。
林田: 低い声が持つ深さや説得力。真実の声を語るのはバリトンですよね。
栗原: そうですね。理想や「勝つぞ!」という高みを目指すのはテノールですけど。
林田: もちろんオペラの花は断然テノールです。テノールが輝くとみんな魅了される。でもバリトンは、影の部分を背負ったり、言いにくい深いことを言ったりする。ある意味、一番おいしい役どころですよ。

●旧来のオペラ界に新しい波を起こすということ
栗原: イタリアのナポリで「ナポリ楽派フェスティバル」というものに参加したことがあります。ペルゴレージの「リヴィエッタとトラコッロ」という二人芝居のオペラをやったんですが、チェンバロと、DJみたいな現代音楽家が即興で音楽を作るという、斬新なプロダクションでした。
林田: すごい!それは面白い話ですね。
栗原: お客さんもゲラゲラ笑っていて。少人数だったので、ナポリだけでなくローマなどにもツアーで回ったんですよ。
林田: そのやり方なら仲間を集めて日本でもできますね。これからのクラシックは、そういう時代に来ていると思います。大勢で大きなものを作るのもいいですが、少人数でフットワーク軽くツアーをする方にも可能性を感じます。
栗原: それで成立するのがオペラですものね。歌とドラマとアンサンブルがあれば、十分オペラになる。
林田: 栗原さんはイタリアでのご経験もナポリのサン・カルロ劇場など素晴らしいものがありますね。そういえば、名歌手マリエッラ・デヴィーアのレッスンも受けられているんですよね。デヴィーアを支えるコレペティ(歌手のコーチをする練習ピアニスト)の存在がすごく重要だと感じませんでしたか?
栗原: コレペティは本当に重要です。普通のピアニストとはまた違う存在で、言葉のことやコンディションのことまで一緒に考えてくれる。
林田: この「サラリーマン金太郎」は、作曲家の神尾憲一さんが、最初からコレペティのように、稽古にずっとピアノを弾きながらついているわけですよね。何しろコンセプトからいっても、今までにないタイプのオペラの成立の仕方です。これを見たオペラ界の人たちが刺激を受けるといいなと思います。
栗原: オペラがなぜメジャーではないのかと考えたとき、一つは題材が高尚に見えがちだからだと思うんです。その点で、誰もが知っている「サラリーマン金太郎」をオペラにすることは、本当に意義のあることです。
林田: オペラを上演することは、世の中に何か波を起こす社会的な行為だと思うんです。今の日本で何を発信するのか、という視点で「サラリーマン金太郎」が選ばれた。まさにぴったりの題材ですね。
栗原: 実はイタリアに留学中も、僕はずっと「サラリーマン金太郎」を読んでいて、どれだけ励まされてきたかわからないくらいなんです。そういう意味でも、これがオペラになるということはすごく嬉しいですし、今回集まった歌手も皆さん本当に素晴らしい方たちばかりで、本番の舞台が待ち遠しくてならないです。

聞き手
音楽評論家 林田直樹
矢島金太郎役
バリトン歌手 栗原峻希